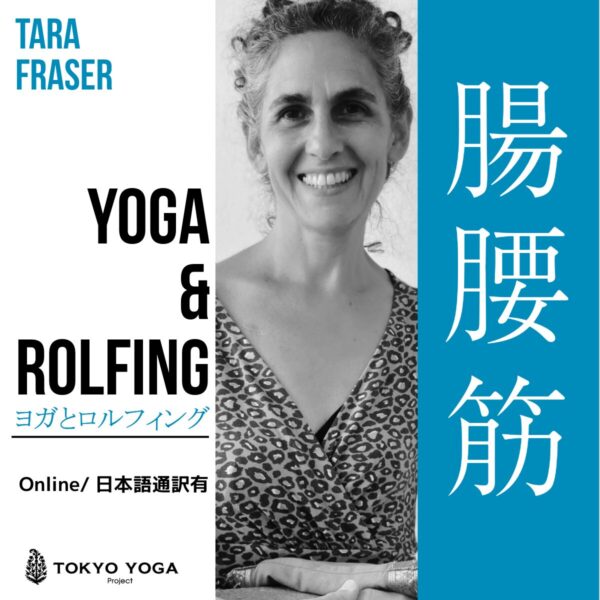Journal
ヨガのある日常のあれこれ
映画『Anuja』をみたんです
先日、Netflixで「アヌジャAnuja」を観ました。
Anujaは23分の短編映画で
今年のアカデミー賞短編実写映画賞にノミネートされた作品です。
ネタバレ、ですが…
インドの縫製工場で(違法だけど)働いている子供の姉妹のお話です。
妹が奨学金をもらえるくらいの才能があるので寄宿舎のある学校への受験をすすめられている。
だけど、受験料をどうする?とか、妹は姉をおいて受験するのか…という話です。
自分が今着ている服ってどこからきてるのかな?
と思ったり、法律が変わったとしてもカースト制が消えたわけではないんだよなと、ありがちですがいろいろ考えました。
国際ヨガデーをつくった首相は表向きカースト制を否定しつつも、より保守的な立場を取っているんですよね。
ヨガは古代インドではカーストの上位階級、特にバラモン(祭司階級)が学ぶ特別な知識でした。
中世になると、ハタ・ヨガの発展やタントラの影響により、より幅広い階層にも開かれるようになりました。
19世紀末から20世紀初頭にかけて、インド国内でもヨガの大衆化が進みつつあった時期に、ヨガは西洋へと伝わり始めました。
その後、20世紀後半になって日本にも。
しかし、インド社会の最下層の人々にとっては、まだ十分に届いていない段階で国際化していったのです。(と私は認識しています)
映画の中の子供がキラキラした表情をみせているのに希望を感じました。
そして、何事にも影と光があるし、どの国でもいろんな問題があるもんね、となんとなくうやむやにしてしまう自分もいます。
それでも、あの映画の中の姉妹が、ヨガウェアなんて着ながらヨガをする豊かな時間を過ごす未来が早くきて欲しいと思いました。
では、Namaste!